- HIKOMA HOME
- INTERVIEW
- 株式会社大起エンゼルヘルプ 介護福祉士 和田 行男


どこまでも「人と人」の仕事。
プロとしての矜持をもち、
人として向きあっていきたい
お世話係的な「介護職」ではなく、
「生活支援師」になりましょう
株式会社大起エンゼルヘルプ
介護福祉士
和田 行男
日本のすぐれたマーケティング企画を表彰する「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」。一般社団法人ACCの主催で、1961年創設という由緒ある賞だ。2019年、そのマーケティング・エフェクティブネス部門グランプリに輝いたのが「注文を間違える料理店」。認知症の高齢者が接客し、注文を間違っておぼえてしまうこともエンターテインメントに昇華。認知症への社会的理解を深め、高齢者の居場所をつくる試みとして、大きな注目をあびた。その仕掛人こそ、和田行男氏だ。介護福祉士として、また介護会社・大起エンゼルヘルプ取締役として、「お世話をするのではなく、自立を支援する」という信念を実践し続ける。

どんな行動からも、本人が『こうしたい』という希望が必ず見えてきます」
介護福祉士の国家資格も、ホームヘルパーの仕事もなかった33年前。介護はおもに育児を終えた女性たちが支えていた時代に、和田氏は前職の鉄道メンテナンスの仕事から、特別養護老人ホームの職員へ転身。介護の世界へと飛び込んだ。「家政婦のような仕事」と認識されていた当時の介護のあり方に、和田氏は強烈に異を唱え続けている。
介護職を始めたころ、上司に「お年寄りにやさしく接しなさい」と言われたことが、僕は非常に疑問でした。
まわりから見て「やさしい」と思われる接し方でも、本意と本位の両面から支援しなければ、それは「やさしさ」ではないのではないか。本意とは、当人の意思や気持ち。本位とは、僕ら専門職から見て必要と思われること。
人間は本来、どこかに多少の不自由があっても、自分で工夫して生活している。本人がやれることまで介護者が取り上げてしまう「やさしさ」は、絶対におかしい――。
僕はこれまで、現場で感じたこういう違和感に対して、「自分はこう思う」を追求してきただけで、それまでの介護の考え方とは少し違っていたかもしれませんが、特別なことをしている意識はありませんでした。
本人が「やってほしい」と望むことを「してあげる」だけでは、メイドさんと変わらないでしょう。また、「したくない」と言っていることを、「わかりました」と肯定するだけでは本人のためにならないこともあります。
本人に歩きたい願望があるなら、「なぜ歩くことを取り戻したいのか」から始まって、「なぜ歩けないのか」を見抜き、「どうやったら前向きに、歩くことへチャレンジさせられるか」を考えてあげるべきではないのか。
「要介護者がいまできることを、どうやったら長く続けられるようにするか」「いまできないことは本当にできないことなのか」「どうやったらできるようになるか」を考えて、実行する。それが私たちの仕事ではないか。
そんな考えに行きついたんですね。生活にどれだけの支援が必要か、その加減を見きわめて、その人の気持ちや能力を引っ張り出す、そのために手立てをとることが大事なことだと思ったんです。
こうした自分の考えを現場で実行できるようになったのは、介護職になって8年目のころからです。
入職した特別養護老人ホームに併設されているデイサービスを担当していました。「デイサービスの活動内容を職員が決める」「あと片づけも掃除もぜんぶ職員がやる」という従来のやり方を1回、すべてぶち壊しました。
認知症だろうが、障がいがあろうが、できることは利用者が自分でやれるように支援する。利用者どうしで助けあえる部分は助けあえるようにする。本人がやりたいことは、やれるカタチを考える。地域社会のなかでの活動に積極的に参加していく。普通の人が普通にやっている「当たり前のこと」から要介護者を遠ざけない支援をめざそうと。
1999年、東京都初の認知症のグループホーム「こもれび」の施設長に就任してからは、これを全面的に展開していきました。
掃除や食事、町内活動なども含め、本人が「生活の主体者」として生きていけるように支援する。テレビの『ニュースステーション』をはじめ、マスコミがたくさん取り上げてくれ、一般の方からは「自分の親をあずけているところと違って、とても楽しそうだ!」と好意的に受け止めてもらえました。でも、同業者からは「認知症や障がいのある人にいろんなことをさせるのは虐待だ! 玄関にカギをかけないなんて危ないじゃないか!」と大バッシング。
でも、僕たちはみんなそうして生きているのに、なぜ介護施設の人だけが保護されなきゃならないのか? 僕はこの信念に対しては、異常にガンコでしたね(笑)。
そうこうするうちに、あるときから厚生労働省も「自立支援」を声高に言うようになって、「虐待のカリスマ」から「自立支援のカリスマ」と呼ばれるようになったわけです。僕自身はまったく変わっていないんですが、勝手に時代のほうが変わっていったんですよ(笑)。


見えているところだけで判断すると、大きく間違ってしまう。
宝探しができるからこそ、この仕事はおもしろいんです」
要介護者一人ひとりに、その人だけの「あるべき姿」を決め、その理想の姿を目指して、かかわっていく。根気も時間もかかる介護のスタイル。こうした地道な作業を支えているものは“好奇心”だと語る和田氏。「この人は、なぜこういう言動をしているのかな?」という人間への好奇心をもっていれば、介護はどこまでも奥深く、クリエイティブな仕事だと――。
僕がいま運営に携わっている大起エンゼルヘルプの介護施設。
そこに入居した方のご家族から、「症状がよくなった」「認知症になりたてのころぐらいまで戻ったみたい」と言われることが多々あります。
僕は要介護者の方と最初に会ったとき、その方の「生きる姿=めざす姿」を自分のなかで決めるんですね。
たとえば、「よし、この方は、町の市場で魚屋さんに冗談を言っている姿をめざすか」とか。そのイメージからの逆算でアプローチを考えていく。学習塾なんかと同じかもしれませんね。
塾の先生たちは「この子はここまで伸びるのでは?」を見きわめ、「そのためにこの問題を解かせてみよう」とチカラを引き出す策を考えるわけでしょう。
この見きわめができるようになったのは、ある程度、介護の経験を積んでから。必ず達成できる目標設定ができるようになりました。
要介護者は、決して後退するばかりではないんです。気持ちや筋肉が戻ってくると、それまでできなかった生活の基本動作が、再びできるようになるケースもめずらしくない。
決めた目標に向かって淡々と取り組めるのは、介護職の強み。
ご家族はしろうとですし、特別な感情があるので、どうしても手を貸したくなってしまうし、めざす姿や手立てを描けない。だから要介護者は家にいるだけだと、もっているチカラを発揮できる環境にならない。
でも、僕らは専門的なサポートをするので、もともともっているチカラを発揮できるようになっていく。そこをめざしているわけです。
たとえば、毎朝、手助けをしてもらって起き上がっていた要介護者がいるとします。でもこれが習慣になってしまうと、自分のチカラで起きられなくなる。
そこで、僕は本人が大好きなおいしいコーヒーをいれ、あえて廊下から「飲みに行きましょう!」と声をかけます。すると自分で起き上がってくるんですね。起き上がれる能力のある人は。
この声がけを「だれがやるか」も重要なポイントです。
認知症の方は特に、人を見るチカラが高い気がしますね。視力が弱い方の聴覚がさえてくるようなものかもしれない。自分にとって味方だと思うと、全然違う姿を見せてくれるし、ヘタにおべっかを使っても、見抜かれます。「自分のことを本気で考えてくれる人だ」と思われなくてはいけない。介護はどこまでも、人と人。それを忘れちゃいけないんです。


ただ機械は素直ですが、人は別の思惑もあって動く。そこがステキなところなんです」
高齢者をその気にさせることで、生きるパワーを刺激していくことを、「そそるチカラ」と名づけた和田氏。「させる」ではないところがミソ。この方法論を編みだすまでには、現場でのさまざまな試行錯誤があったという。自立支援のパイオニアとなるまでのヒストリーを聞いた。
介護の世界に飛び込んだのは33年前、国鉄の…って言っても若い人は知らないかな(笑)。いまのJRの前身です。その職員として、車両のメンテナンスに携わっていました。
そのとき「障がいをもった方々も、列車で旅をしよう」という企画にボランティアとしてかかわったのがきっかけです。この運動を通じて、「ノーマライゼーション」という言葉を知りました。当時の街中には障がい者用のトイレもエレベーターもない、だから障がいをもつ人が外に出られない。本人たちも「ひとさまに恥ずかしい姿を見せたくないから…」なんていう時代でした。
でも、そんな障がい者たちが列車に乗って旅をする。この取り組みが全国各地で行われるなかで、街のほうが変わっていくんです。トイレもエレベーターもできる。本人たちが世の中を動かしていく。10年間その変遷を見るなかで、福祉の仕事は悪くないな、と。「僕でもなにかできることがあるかもしれないな」と思い、高齢者介護の世界の門を叩きました。
認知症の高齢者の方についての考え方も、鉄道時代の経験がもとになっています。僕にとって社会福祉って「人々がハッピーになること」的なイメージでしたが、当時の認知症の方々はどう見てもハッピーじゃない。
だって、施設のなかに閉じ込められているんですから。「障がい者の方々が旅に出ることで社会が変わったように、認知症の方々も社会生活を営めるように支援することで、世の中変わるのでは?」と。
そう思ったら、障がいをもっている人も、認知症の人も、“普通”と呼ばれている人々と、ちょっとした「ズレ」があって、その「ズレ」を埋めるようなことを社会の側が用意すればいいんじゃないかと。
ただ、障がい者の場合、「車いすを使っている人」という具合に、ある程度、分類が可能ですけれど、認知症の場合は百人百様。「車いすの利用者のことを考えて、道の段差をなくしましょう」というような、たいていの人に当てはまるズレの埋め方がない。一人ひとり違ったやり方で埋めていかなければいけない。それこそが人間のおもしろさでもあるんですけれど。
僕が最初に勤めた特別養護老人ホームでのこと。あるとき、夜中に「なにかいる。見える! こわい!」と訴える要介護者がいて、周囲から問題児あつかいされていたんです。
こちら側にとって「見えないものが、この人には見えること」をいったん肯定して手立てを講じないとズレが埋まらない。
僕はそう気づき、「まかしとけ、俺がやっつけてやるから」と壁を蹴り飛ばして。「やっつけてきた!」と言ってみたんです。すると、その方は本当にうれしそうに「ありがとう」と両手を握ってくれて。その後は寝られるようになったんですね。これでいろんなことが拓けていきました。


“認知症の介護士”ってめずらしいから注目されて、私の言うことをみなさん、聞いてくれるんじゃないかって。
それぐらい、業界に対して発言力をもちたいと思いつめていました」
和田氏がどんなに業界のあるべき姿について発信をしても、「たかが介護士ごときが言っていること」と一蹴された時代もあったという。しかし、テレビ番組で自立支援に取り組む姿が取り上げられたり、認知症の高齢者が接客する「注文を間違える料理店」の企画がヒットしたりするなか、和田氏は一躍、「時の人」に。業界に影響を与える存在になった現在、同氏は業界の未来に対してどんな想いを抱いているのだろうか。
NHKの番組『プロフェッショナル』に出演させていただいたとき、「プロフェッショナルとは?」という問いがあって。僕は「自問自答」と答えました。「なぜうまくいったのか、なぜうまくいかなかったのか」の答えを、全部ストックしていく。そして自分の出した答えに対しても、自分でさらに問いを続けられる人。それこそがプロフェッショナルであり、プロの介護職ではないでしょうか。時間どおりにお世話する人になりたいなら、一流のメイドを目指せばいい。でも僕は介護職。だから自問自答していく。
もっとも、僕は介護という言葉は好きじゃないんです。
いまやっている仕事の内容を考えると、「介護」といういい方をやめたほうがいいと考えています。介護のイメージを市民講演会なんかで聞くと、多くの人が「してもらうこと」と思っているし、働く人も「してあげること」と考えていたりします。
人の手を借りなくては生きていけない状態になっても、自分のチカラを発揮して生きていけるようにする、「必要なときに・必要なことを・必要な分」届けることが仕事で、単純にしてあげてできることまで奪ってしまうことではないはずです。だから、「生活支援師」くらいがいいんじゃないかな。これからも「人が人として生きていくための支援活動」にただひたすら挑み、追いかけていく。それが僕のビジョンです。
『プロフェッショナル』を見てくださった方々から、「すごくいい顔をしていた、お年寄りが好きなんですね」と言われたことがありますが、僕は年寄りが好きなのではなく、「その場面で必要な顔をしていただけ」のことです。それが仕事ですから。
「職業人としての自分を高める」「専門家としてひたすら追求する」という姿勢は、どんな職業でも大事なこと。でも介護業界は、そこが少し弱い気がします。
介護はその昔「お世話」でしたし、制度的にも誰でもできる仕事になっていますから。
国民生活に不可欠なインフラとして社会的に位置づけ、介護の仕事も医療のように専門職による特別なこととして待遇面も含めて確立していかなければ、志の高い人は集まってこないと思います。
仕事の中身自体を大きく見直して、「職業人としての介護職」に誇りをもてるような、「さすがですね」とご家族に感嘆されるような仕事にしていきたいですね。
介護実習生から「私も先輩のように、おむつ交換が早くできる一人前の介護職になりたい」なんていう言葉を聞いたことがありますが、本当にそれが「よい介護なのか」という観点はもっていてほしい。
人が生きるというのはどういうことか。生きることを支援するとはどういうことか。国家資格である介護福祉士をめざす方、とくに次代を担う若い方には考えていただければと思います。
人間は、本当におもしろい。
最後まで人として生きるチカラを
引き出すのが僕の使命です


プロフィール
1955年、高知県生まれ。日本国有鉄道(現:JRグループ)職員として車両修繕に従事したのち、1987年に介護業界に転身。特別養護老人ホーム勤務などを経て、1999年に東京都初の認知症高齢者グループホーム「こもれび」の施設長に就任。2003年から株式会社大起エンゼルヘルプで、デイサービスやグループホーム、小規模多機能ホームなどを統括。認知症ケアについて、従来にないアプローチを開拓し続けると同時に、「注文を間違える料理店」など認知症への社会理解を深めるさまざま活動を行っている。著書・共著書に、『大逆転の痴呆ケア』『認知症になる僕たちへ』『認知症開花支援』『ダメ出し認知症ケア』(以上4点、中央法規出版)、『だいじょうぶ認知症』(朝日新聞出版)など。
事業所概要
| 社名 | 株式会社大起エンゼルヘルプ |
|---|---|
| 住所 | 東京都荒川区東尾久1-1-4 5階 |
| URL | http://www.enzeru.co.jp/ |
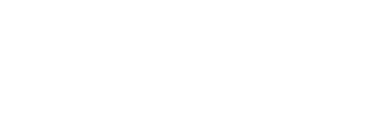
 高齢者の「自宅で暮らしたい」を
高齢者の「自宅で暮らしたい」を 頼れる先輩職員の方々がいるから、
頼れる先輩職員の方々がいるから、 利用者さんの「お世話をする」ではなく、
利用者さんの「お世話をする」ではなく、